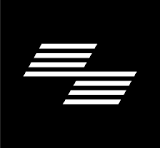急速に拡大しているHYROX
世界最大級のインドアフィットネス競技として近年急速に拡大しているHYROX(ハイロックス)は2017年11月にドイツ・ハンブルクで初開催され、当初の参加者は約650人でした 。
そこから数年で急速に拡大し、2023年には世界中で65のレースが開催され、年間延べ17万5千人もの参加者を集めています(ロンドンの大会だけで約2万4千人が参加) 。
わずかな期間で開催地域は18か国・60以上の都市に広がり、1大会あたり最大で12,000人の参加者を動員する規模に成長しました 。
公式発表によれば、2025年には世界80以上の都市で大会が行われ、延べ55万人の競技者と35万人の観客を動員する計画とされており、その勢いが伺えます 。日本では2025年8月にパシフィコ横浜で初開催が予定されており、観客動員は5,000人規模を見込んでいます 。
一方、障害物レースのスパルタンレースは2010年前後に米国で始まり、現在では世界42か国で年間100万人以上が参加する大規模イベントとなっています 。
日本では2017年前後に初上陸し、約5年間で累計17大会・延べ6万5千人の参加者を記録しています 。
新型コロナ禍を経て大会数・参加者数は再び拡大傾向にあり、2024年シーズンだけで延べ約2万人が参加しました(昨年末の沖縄大会では約4,000人が出場) 。
日本国内の各スパルタン大会は一大会あたり数千人規模の参加者が集まるのが通例です。例えば新潟県湯沢町で毎年開催される大会では約4,000人が出走し、家族や友人を含めれば訪問者は8,000人近くに及びます 。
日本の市民マラソン大会は既に定着した文化であり、参加者規模も桁違いに大きくなっています。主要な都市マラソン大会では毎回数万人のランナーが走っており、例えば東京マラソンでは約3万5千人、大阪マラソンで約3万2千人、那覇マラソンで約3万人が参加します 。
直近5年間では2020~2021年にかけて新型コロナの影響で多くの大会が中止・縮小となりましたが、2023~2024年には主要大会がほぼ平常規模で開催されるまで回復しています。
長期的に見ても国内のマラソン大会数は増加傾向にあり、2004年には全国で49大会だったフルマラソンが2023年には89大会に増えています 。
このことはランニング人気の根強さを示しています。ランニングに親しむ人口も数百万規模で、2022年には年に1回以上ジョギング・ランニングを行った人が推計877万人に上りました 。こうした裾野の広さがマラソン大会の大量参加を支えています。
地域経済への影響
大規模マラソン大会は開催地の地域経済にも大きな恩恵をもたらします。例えば東京マラソンでは、2024年大会において日本国内で約526億円の経済波及効果があったと推計されています 。さらに2025年大会では外国人ランナーの増加もあって経済効果は約787億円に拡大しており 、一大会で莫大な消費を生み出すことが分かります。この経済効果には、何万もの参加者・応援者による交通費、宿泊、飲食、買い物などの消費が含まれています。大阪や名古屋など他の都市マラソンでも毎回多数の来訪者があり、地域の宿泊・観光需要を喚起するなどスポーツツーリズムの柱となっています。
日本で開催されたスパルタンレースのスタート。多数の参加者が自然の中で障害物レースに挑戦している。地方開催の大会では、参加者は仲間と共に遠征し大会後に宿泊・観光もするため、地域に落とす経済効果も大きいとされる 。
スパルタンレースのような障害物レースも、規模ではマラソンに及ばないものの開催地の経済活性化に貢献しています。例えば愛知県の豊田スタジアムで開催されたスパルタンレースでは、近隣の宿泊施設や飲食店が満室となり、約3億5,000万円の経済波及効果があったと報告されています 。このように、一大会が数千人規模でも宿泊や飲食によって地域に数億円の消費をもたらすケースがあることが分かります。
また、新潟県湯沢町で継続開催されているスパルタンレースは、当初は地元の反応が薄かったものの、現在では毎年約8,000人(参加者4,000人+同行者)が町を訪れるイベントに成長し 、地元の飲食店や宿泊業も熱烈に大会を歓迎するようになっています 。参加者は仲間や家族とともに遠征し、日帰りせず宿泊する人が多いため、レース後にはグループで飲食を楽しみ温泉に入り、翌日は観光に繰り出すといった動きが見られます 。こうした滞在型の消費によって開催地域全体への経済効果は非常に大きく、スパルタンレースを通じてスポーツツーリズムで地方創生を実現しようという想いも運営側にはあります 。実際、人気の高まりに伴い自治体から大会誘致の声がかかることも増えており、地域振興や交流人口拡大への波及効果が期待されています 。
HYROXに関しては、日本ではこれから本格展開という段階であり、現時点で具体的な経済波及効果のデータはありません。横浜での初大会は国内のフィットネス愛好者中心の参加が見込まれ、都市部での開催ということもあって、観光振興の面では地方開催のレースほど顕著ではないかもしれません。それでも、5,000人の観客動員が見込まれること から会場周辺での消費は一定程度発生するでしょうし、今後大会数が増えて各地で開催されるようになれば、他のスポーツイベント同様にスポーツツーリズムとしての効果も期待できるでしょう。また、HYROXは地元ジムとの提携やグローバルスポンサー(Red BullやPUMAなど)の協賛によって運営される予定であり、それ自体がフィットネス産業内での新たな経済活動やスポンサーシップの盛り上がりにつながる可能性もあります。
HYROXがフィットネス文化として広がる可能性
日本においてマラソンはすでに確立されたフィットネス文化の一部と言えます。2000年代以降の“ランニングブーム”により大会数・参加者数は飛躍的に増加し、今では国内に多数のマラソン大会が根付いています 。東京マラソンに代表される大規模大会はテレビ中継される国民的行事として定着し、完走することが市民にとって一種の自己実現の目標ともなっています。またチャリティ参加やボランティア活動などを通じ、社会・コミュニティとの結びつきも強いイベントになっています。
一方のスパルタンレースは、マラソンほどの一般的知名度はないものの、この数年で熱心なコミュニティを築くことに成功しています。その過酷さや非日常性に魅了された参加者が次々と仲間を誘い、新たなファン層を拡大する好循環が生まれていると考えられます。実際、運営会社のSRJによれば、最近では自治体から開催の打診を受けたり、初対面の相手から「スパルタンレース知っています!」と言われる機会が増えるなど、認知度も着実に向上しました 。
スパルタンレースは単なる競技会ではなく「自分自身が変わっていくことを楽しむ」ライフスタイルの実現を目指すものと位置付けられており 、キッズレースの導入や家族ぐるみで参加できるカテゴリー設定にも力を入れています。
こうした取り組みは、障害物レースの価値観を次世代や家族単位で広め、コミュニティを拡大していく狙いがあると言えるでしょう。継続開催してきた地域では、店先に大会の旗を掲げたり大会Tシャツを着て応援に駆け付けたりする地元住民も現れるようになり、長年続けてきたからこそ地域に根付いた光景も生まれています 。
では、HYROXはこうした文化的存在感を今後築けるでしょうか。その可能性は十分にあります。第一に、HYROXは初心者から上級者まで「誰でも参加できる」ことを特徴としており 、日頃ジムでトレーニングしている一般層も巻き込める間口の広い競技です。普段のフィットネストレーニング(1kmラン+8種目のワークアウト)をそのまま競技化したシンプルな形式であるため、エリートアスリートだけでなく幅広い層が挑戦しやすい土壌があります。競技内容も「1km走ってワークアウトを8セット繰り返すだけ」という分かりやすいルールで 、誰にでも取り組み方がイメージしやすい反面、体力的には非常にハードで達成感を得られるバランスになっています。このシンプルさとチャレンジ精神の両立は、新たな目標を求めるフィットネス層に響く可能性があります。
第二に、コミュニティ形成という要素が挙げられます。HYROX初開催により国内で新たな参加者同士のコミュニティが生まれるだろうと期待されています 。同じ目標を持つ仲間がつながり、互いに競い高め合う環境は、ランニングクラブやスパルタンレースのチーム文化でも実証されている通り、そのスポーツを長く定着させる原動力となります。実際、HYROX運営側も日本で文化を根付かせることに意欲的です。HYROXアジア太平洋マネージングディレクターのゲリー・ワン氏は「HYROXは常に拡大を続け、新たな市場へユニークなフィットネス体験を提供したいと考えています。日本はフィットネス文化が成長し、革新的な挑戦を受け入れる国であり、大きなチャンスです。HYROXのファンクショナル・エクササイズと持久力の融合は、日本のフィットネス愛好家に深く響くと信じています。現地のジムと協力し、日本での存在感を高めるとともに、フィットネス・コミュニティの活性化を促進し、参加と継続を支援していきます。この取り組みは、HYROXをフィットネスコンペティションのグローバルリーダーとしてさらに確立するものとなるでしょう」とコメントしています 。こうした発言からは、単発のイベントに留まらず長期的に日本のフィットネスシーンに溶け込もうとする戦略が伺えます。
もっとも、HYROXがマラソンのような国民的スポーツ文化や、スパルタンレースのような独自の地位にまで成長するには課題もあるでしょう。既存のマラソン・トライアスロン・クロスフィット競技など多彩な選択肢がある中で、自身の競技ならではの魅力を打ち出し、参加者の裾野を広げていく必要があります。それでも、国際的な盛り上がりや主要ブランドの協賛といった初動の状況は追い風ですし、日頃のトレーニング成果を試せる競技コンセプトは他のスポーツを補完する位置付けでもあります。総合すると、日本でのHYROXはまだ始まったばかりですが、参加者数の拡大とコミュニティ醸成が順調に進めば、将来的にマラソンやスパルタンレースに並ぶ新たなフィットネス文化の柱となり得ます。日本のフィットネス愛好家がこの競技の持つ挑戦精神と仲間意識に共感し、予想通り受け入れれば 、国内に“HYROX文化”が根付いていき、さらなるフィットネスムーブメントの一翼を担う可能性は十分にあるでしょう。
参考文献・出典:
・BRAVE FITNESS GYM「ついに初の日本開催決定!世界が熱狂するフィットネスレースHYROXとは?」 (2024年)
・PR TIMES「世界最大級フィットネスレース『HYROX』日本初上陸プレスリリース」 (2025年)
・HYROX JAPAN公式サイト「HYROX:すべての人のためのフィットネス競技」
・アットプレス「Spartan Race 2024年年間スケジュール発表」プレスリリース (2024年)
・HALF TIMEマガジン「スパルタンレースが日本で成功」インタビュー (2025年)
・HALF TIMEマガジン 同上
・HALF TIMEマガジン 同上
・岡田将和ブログ「スパルタンレースBEAST。」 (2023年)
・東京マラソン財団「東京マラソン2024の経済波及効果について」ニュース (2024年)
・東京マラソン財団「東京マラソン2025の経済波及効果について」ニュース (2025年)
・RUNNET「過去20年間の市民マラソン界の動向」 (2023年)
・HonKawaデータ「日本のマラソン大会 参加人数」
・笹川スポーツ財団「ジョギング・ランニング人口」統計 (2022年)
・その他、HYROX公式Instagram、スポーツメディア記事、各大会公式発表資料 等。