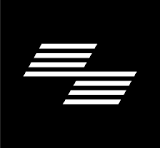初心者・高齢者でも挑戦できる!HYROXリレー形式の魅力
フィットネスレース「HYROX(ハイロックス)」は、世界中で人気を集めている新しい形のトレーニングイベントです。
「きつそう」「自分には無理かも」と思われがちなこの競技。実は、初心者や高齢者でも無理なく挑戦できる“リレー形式”が用意されており、日本でも注目が高まっています。
この記事では、HYROXのリレー形式とはどんなものなのか、なぜ高齢者や運動初心者に最適なのか、そしてどんな社会的意義があるのかを解説します。
HYROXとは?
HYROXは、ドイツ発祥のインドアフィットネスレースで、エルゴマシン(ローイング・スキーなど)+ファンクショナルトレーニングを組み合わせた全8種目のトレーニング競技です。
種目ごとに「ラン→ワークアウト→ラン…」と繰り返す構成で、タイムを競うスタイル。世界65都市以上で開催され、年間30万人以上が参加するまでに成長しています。
リレー形式とは?
通常のHYROXレースは個人で全種目をこなしますが、「リレー形式」は4人1組のチームで種目を分担して行う方式です。
- 各人が約2種目+2回のランを担当(順番も自由!)
- 仲間とタスキを繋ぐような形式
- 一人あたりの負担が1/4に軽減される
これにより、運動初心者・体力に不安のある方でも、チームの一員として競技に参加できます。
初心者・高齢者でも挑戦できる理由
1. 身体的負荷が大幅に軽減
一人で全てをこなす必要がないため、心肺機能・筋力の負荷が分散されます。実際に、高齢者施設や企業の健康推進イベントでも応用しやすい構成です。
2. チームの安心感
仲間と励まし合いながらゴールを目指すリレー形式は、精神的なハードルも下げてくれます。「1人じゃない」というのは、特に初参加者にとって心強いポイント。
3. 社会的つながりの促進
高齢者にとっての「孤立」は大きな課題です。HYROXリレーを通じて仲間と出会い、運動だけでなくコミュニティの形成にも繋がります。
事例紹介:80歳代の参加者も海外では活躍!
アメリカやドイツでは、なんと80代の参加者もリレー形式で完走を果たしています。
公式インスタグラムでは「#HYROXGrandma」などのタグで称賛されており、世界中の高齢者に勇気を与えています。
高齢化社会の日本におけるHYROXの意義
健康寿命の延伸に貢献
日本では「健康寿命の延伸」が重要課題。運動習慣の形成はその鍵となります。HYROXは楽しみながら運動できる場として、新たなアプローチになり得ます。
医療費削減・社会保障の負担軽減
高齢者の運動不足による医療費負担は、国全体の問題です。HYROXのような参加型イベントによる予防的アプローチは、その解決の一手となる可能性があります。
具体的なトレーニング例(リレー出場を目指す方へ)
「興味はあるけど、体力に自信がない…」という方向けに、簡単な準備トレーニングを紹介します。
- ウォールボール(軽量):10〜20回を目安
- ステップランジ:15〜30回
- スキーエルゴ・ロウエルゴ:各100〜200m
- ウォーキング or 軽ジョグ:週2〜3回
まずはジムでの「PFT(フィジカルフィットネステスト)」に参加して、自分の現在地を知ることから始めましょう。
HYROXは観光とも相性が良い?
「旅先で運動したい」という外国人観光客も多く、HYROXジムは観光客にも人気です。ホテルと連携し、「滞在中にトレーニングできる場」として提供する取り組みも進んでいます。
Q&A:よくある質問
Q:何歳まで出場できますか?
A:年齢制限はありません。60代・70代の出場者も増えています。
Q:仲間がいなくても出られますか?
A:はい。ジムでマッチングしたり、イベント運営側がチームを組んでくれる場合もあります。
Q:全く運動経験がなくても大丈夫?
A:はい。レベルに応じたトレーニングを事前に受けられる環境が整っています。
実際に体験してみよう!
ジムフィールドではHYROXのリレー形式に対応した体験レッスンや練習会を定期的に開催しています。
👉 体験予約はこちら
まとめ:HYROXリレーは“誰でも挑戦できる”フィットネスイベント
高齢者でも、運動初心者でも、「仲間と挑戦する」ことができるHYROXリレー。
健康・コミュニティ・生きがいを同時に手に入れることができるこの仕組みは、新しい健康文化の扉を開いてくれます。
今後、地域や行政とも連携し、より多くの人がHYROXを通じて「健康で楽しい毎日」を手に入れる日も近いでしょう。